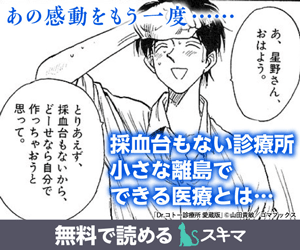なあ、カエル。おまえぴょこぴょこし過ぎじゃね(泣)(恋愛私小説Vol.1)
早口言葉に泣いた夜、の話。


それ言えたら付き合ってあげる
カエルぴょこぴょこ三ぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこ六ぴょこぴょこ。この早口言葉がどうしても言えない。学生時代は、言えないことを自虐的に話してちょっとした笑いをとっていた。
イタリアンレストランのバイト仲間と笑っていたのを小耳にはさんだのだろう、厨房の片隅で四つ年上の社員のお姉さんから「カエルぴょこぴょこ三回言えたら付き合ってあげる」と耳うちされたのだった。
お姉さんはとにかくキレイだった。そしてとてつもなく気の強い人でもあった。バイトの僕へ、手にした調理用ナイフの先で伝票をつついて差出したりするような横柄なところもあった。当時の僕にはそういうすべてがかっこいいおとなの女性に思えたし、なにより本当に美人なので僕はあこがれを抱いていた。若干ヤラしい僕の視線にもきっと彼女は気づいていただろう。だから、きっと僕をからかったのだと思う。
その夜アパートで独り猛特訓するがぜんぜんできない。「三」の後の「ぴ」を噛んでしまう。たまにそこをクリアできても「六」を「む」と言えないし、「む」の後の「ぴょこ」はもう絶望的だった。そりゃそうだ、小学生のころから一度だってちゃんと言えたためしがないのだ。そう簡単に克服できるわけもない。
「隣の客はよく柿食う客だ、じゃダメ?」ときくと、「もう言えてんじゃん。そんな簡単なのは駄目」。「坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、は?」「言えてんじゃん。だめ駄目」。「バス、ガスばくはっ、ああ、これむずい、これを言えるようにしてくるからどうでしょう?」「言えないふりすな! 論外だわ」
「ミミズにょろにょろ三にょろにょろ合わせてにょろにょろ六にょろにょろ、この早口から始めてみな」と彼女からご提案があった。確かにぴょこがにょろに替わっただけでかなり言いやすくなった。少しの練習でなんとなく言えるようになったので披露する。
一回目二回目まではなんなく言えるのに三回目の最後の六にょろでどうしても噛んでしまう。緊張のせいだろうか。「あーダメダメ、鈍くさいなあ」彼女に罵られながら、それでもとにかく成功にこぎつけた。
「ようやくか、遅っ。まあいいわ。次の段階は、カエるぴょこぴょこじゃなくて、カエルひょこひょこでやってみ。まったく手間がかかる子だわ」呆れたように、少しアンニュイな冷淡さも醸して彼女が言った。そのとき僕はようやくわかったのだ、ああこの人は間違いなくドSなんだと。


やっぱ6回はぴょこぴょこし過ぎだよ、カエル君
カエルひょこひょこは、ミミズにょろにょろよりハードルは上がっていたが、ぴょこぴょこよりはまだ言いやすく、練習を重ねると、成功する確率もあがっていった。「カエルひょこひょこ三ひょこひょこ合わせてひょこひょこ六ひょこひょこ」やはり3回目の「六」とその後の「ひょこ」でつまずくことが多かったが、何度かのチャレンジの結果、女王様の前で成功することができた。生物学的の下等なミミズから両生類のカエルに格上げできたようで僕も少し誇らしくなった。
「さあ、ぴょこぴょこも頑張んな」女王様にクールに命じられたけれど、たまに2回目までは偶然成功したとしても、やはりどうしても三回目の「六」とその後のぴょこを噛んでしまうのだった。どうしても出来ない。母さん、なぜ僕を活舌悪く産んだんだ!と母親を恨んでしまう瞬間もあった。まったく筋違いだったね、お母さん、ごめんね。
けっきょく僕は、カエルぴょこぴょこは言い切ることはできなかった。「でもよく頑張ったよ、いい子ね、付き合ったげるね」という彼女のツンからのデレなやさしいお声を期待したけれど、そんなドラマみたいな逆転劇もなく、彼女と僕の間に何も進展はありはしなかった。
今も時々、想うことがある。もしもあのとき、偶然でも三回連続ぴょこぴょこが言えたら、お姉さまとお付き合いできたのだろうか、と。でもなあ、もしそうなってたら、まずハグに至るために、ああしろこうしろという女王様的な課題があって、それをクリアしたら、次はまたキスまでに難題が課されて、さらに次のステップへは・・・ きっと困難の連続で大変だったろうなと思う。そういうの嫌だな、めんどくさいなと思う反面、それもちょっとありだったかなと思う自分もいたりして。僕、自覚なかったけど、実はドМなのかもしれん。えー、今さら、どないしょ💦
了