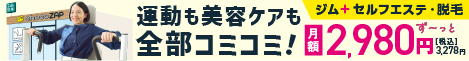マリッジブルーと暴走族(恋愛私小説Vol.2)
師走になると想い出す恋の話



雪の中で僕らが手をつなぐまで
毎年、師走になると思い出す景色がある━━━
大晦日の前夜を「大晦日イヴ」と呼んでいいのかどうかは知らないけれど、年も押し迫ったそのイブの夜に、僕は、彼女と出会った。
「大変やね」と声をかけたのは僕だった。
彼女と彼女の友達は、さっきから何人もの男性から声をかけられていて、その誘いをことごとく断っている様子を、僕は居酒屋の隣の席でずっと気にしていた。その迷惑そうな雰囲気をみかねて、つい声掛けをしてしまったのだけど、あとで考えると、この僕の行為もナンパと思われかねないものだった。そのときはぜんぜんそんな気はなかったけれど。いや、ぜんぜんというとたぶん嘘になる。
こちらを向いた彼女の顔は困惑と笑顔が半々、というような表情にみえた。
「地元のひとなん?」とりあえず尋ねてみる。
「そうよ」と彼女の友達が言い、あんたらは?と聞き返してくれた。ナンパ野郎達とは線引きしてくれたのかもしれない。
「正月休みで帰省しとるとこ。こいつは幼稚園からのツレ」一緒に飲んでる親友を紹介した。
ツレは中部地方で会社員を、僕は東京で作家をやっていた。彼女らは地元で働いていると言った。二十代半ばの僕らよりほんの少しだけ年下だった。
それから僕らは席をさらにくっつけて4人で飲んだ。
彼女の友達はとても快活で明るく、みんなに会話をまわしてくれるようなひとだった。反対に、彼女はひかえめで、おとなしかった。口数も少ない。でも誰かの話にはそっと寄り添っていつもほのかな笑顔をうかべていた。そんな彼女に僕は好印象を持った。ただ、彼女の笑顔にはなんとなく影があるような気がして、そこが少し気になっていた。
「あのこね、春に結婚するんよ」
彼女がトイレに立ったとき、友達が言った。
「でもね、マリッジブルーっていうのんかなあ、最近ちょっと元気なさげだったんで、話きいてあげよう思って飲みにきたんよね」サワーグラスの縁を指で撫でている。
「そしたら、うるさい男どもが邪魔しに来る、来る、来る。ほんと、もう、ウザッって感じよねえ。あんたら、ただ女っ気がほしいだけでしょ、って」
「ごめん、僕らもお邪魔やった?」
「ううん、あのこの顔みたら嫌そうじゃなかったから、大丈夫と思って」
「顔みてそんなんすぐ分かるん?」
「うちらも幼馴染やもん。実際、楽しんでるみたいやし、よかった」
楽しんでくれてるのか。ほんとにそうならいいけれど。
2時間程飲んだだろうか、お開きということになり、会計をすまし、僕らは二人を駅まで送ると言った。連絡先は交換しなかった。本当はしたかったけれど、婚約中のひとにそれをきくのはいけないことだという想いもあった。
駅の改札の手前で、彼女が僕のコートの肘をつかんだ。僕らは立ち止まった。
「もう少しだけ、お話できませんか?」彼女がうつむいたまま言った。
居酒屋でみた彼女もどちらかというと小柄なほうだったけれど、そのときの彼女はさらにあどけなく、まるで少女のように感じられた。なによりも彼女からそんなセリフが出てくるとは思ってもいなかったから、僕は少し戸惑った。
親友と友達は腕を組んではしゃぎながら改札へ入ろうとしているところだった。
「わるいー。彼女、借りる。もう1件だけ飲んで送ってくから。ごめん、先、帰って」二人に告げて、僕は彼女をまた繁華街へと促した。



カフェのようなバーのような店に入った。そこが駅からすぐだったのと、落ち着いて話せそうな雰囲気だったからだ。カウンターに座る。他の止まり木にはお客さんは誰もいなかった。
慣れないカクテルをオーダーする。
お互いに饒舌なタイプではないので少しずつだけれど、何気ない会話を僕らは重ねた。話していると、なんだか心の温度が少しあがっているような気がした。そんな中、
「ゆきちゃんからたぶん聞いてると思うんですけど、わたし3月に結婚するんです」まるで切実なカミングアウトのように彼女が言った。
「そうだってね、おめでとう」なんでもないように僕は応えた。
「みんな、そう言ってくれるんですけど、なんか素直にありがとうって言えなくって」とても寂しそうに笑う。
「相手に不満とか不安とかなにかあるの?」
「まじめでやさしいし、きっと幸せにしてくれると思うんです」
「好きなんでしょ?」
「好き、ですけど・・・」
「自信がなくなった?」
「わたし、今まで本当の恋愛をしたことがないから・・・」
「本当の恋愛?」
「それに、わたし、たとえばあなたのように好きな道でがんばってみたこともないし、このままでいいのかなって」
「僕なんて、たいしてがんばってもないし、なにもうまくいってないよ」
「わたし知っている曲もありますし、すごいと思います」
「いや、そんなことはぜんぜんないよ」
僕はまだ結婚したこともなかったし、マリッジブルーという言葉しか知らなかったけれど、ほんと切実に、ダイレクトに、僕の心に彼女の悩む気持ちは伝わってきた。けれど、未熟な僕には彼女を救うような特別な言葉も特効薬も何ひとつない。
多くの人がこれを乗り越えて幸せになっていくんだろう、時間が解決する案件であるとしか考えられない自分が情けなかった。
終電時間も近くなってきて、店を出た。改札へ向かおうとする僕。ふと気づくと彼女がいない。振り向くと、彼女は店の前に立ちすくんでいた。
「どうしたの?」
「今日はこのまま一緒にいたい」それは宣言に近い言い方だった。
彼女の中にくすぶっているいろんなブルーを破壊するための宣言なのかもしれなかった。少なくとも僕はそう感じた。
「分かった、泊まれるとこ探そう」
駅近辺のホテルを探してみたが、時期が時期なだけにどこにも空室がない。
「どこもだめだね。もう終電だし、今日は帰ろう」
これに対する彼女の返答は、あれからずっとずっとずっと僕の胸に突き刺さっている。
彼女は言った、
「今日このまま帰ったら私は一生後悔すると思う」


ふわり、ふわり、舞うような、細かい粉雪が降り始めていた。
僕らは繁華街を通り抜け、郊外へと続く県道へ向かって歩いていた。郊外まで行けば泊まれるホテルがあるかもしれない。駅前にはタクシー待ちの行列が長く伸びていてそれを待つには何時間かかるかわからなかった。
ぽつり、ぽつり、時々たわいもない話を白い息にまぜながら、僕らは歩いた。
県道に出て歩いていると、遠くから派手なクラクションとエンジン音が近づいてくるのが分かった。ヤバイ、と僕は思った。田舎の県道、正月前のこの時期、当時全盛だった暴走族の群れがやってくることを確信したからだ。
暴走族はすぐにやってきた。バイクと、時々自動車も、百台・二百台どころではない、おびただしい数。けたたましいクラクション、爆音、嬌声。旗を振っている者、叫び声をあげている男、蛇行しながら、無数の暴走族車が道路を埋め尽くしていく。
僕らには逃げる場所も、隠れるところもなかった。ただ歩道を歩くしかない。すぐ横を爆音をたてながら通っていく暴走族に、僕は恐怖で身をかたくしながら、それでもなにかあったら「この子だけはなんとか守ろう」と、正直、命もかける覚悟を固めていた。頼む、このまま、なにごともなく、通り過ぎてくれ、頼む、頼む。そのとき彼女がどういう表情でいたのか、まったく記憶にない。そんな余裕はまったくなかった。
どれくらいの時間が経ったか。暴走族の最後尾が僕らの横を通りすぎて行った。その列が数十メートル先へ行ったとき、はじめて生きた心地がついた。そのとき、みた景色。長い県道をおびただしい数のテールランプが流れていくのがとてもきれいで、無事であるという安心感も加わったせいか、白く舞う雪の中で流れる真っ赤なテールランプが涙が出るほど美しかったことを覚えている。
放心から我に返ると、僕と彼女が手をつないでいることに気づいた。そうか、いろんなことに確かな答えはすぐに出ないとしても、まずできることはこれだったんじゃないか。手のひらの哀しいほどの冷たさとわずかな温もりが嬉しかった。
雪の粒は大きさを増し、遠くの木々に雪だまりを作り始めていた。
僕らは手をつないだまま県道をまた歩き始めた。
了